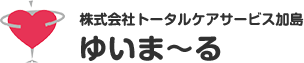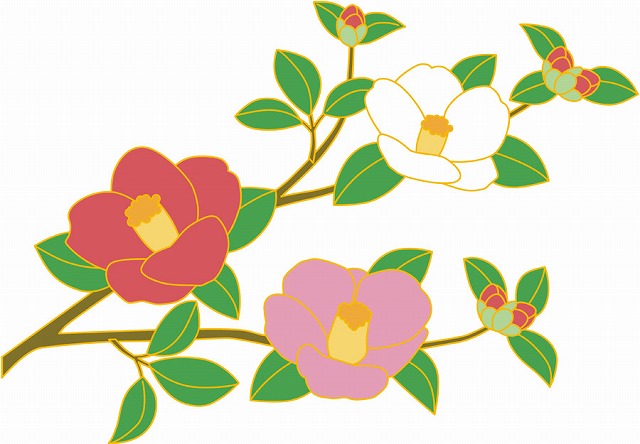コロナ禍から2年以上が経過して、以前と同じように人が外出するようになりました。
外国からの観光客も増えています。
そして今や日本で暮らす人は、国籍、年齢、性別、外見、価値観、能力や性格、育った環境なども様々です。
でもそこでは、生活を営んでいる多数派の人たちによって社会がつくられており、少数派の人たちにとっては、不便さや困惑を生む障壁(バリア)が存在しています。
障害のある人や高齢者にとっても同様で、誰もが自由に楽しみたくてもまだまだ社会には取り除かなくてはならないバリアがあります。
どんなことにバリアを感じているのか。
大きく分けて4つあります。
(1) 公共交通機関、道路、建物で段差、坂道など移動に困ってしまう物理的なバリア。
(2) 就職、資格試験などで障害のある人が能力以前の段階で機会を奪われてしまう制度的なバリア。
(3) 視覚、聴覚障害の方に伝え方が不十分であるために、必要な情報が得られない文化・情報面でのバリア。
(4) 周囲からの心ない言葉、偏見や差別、無関心など障害のある人を受け入れない意識上のバリア。
街中では(1)のバリアをなくす為に、様々な取り組みが進められています。
エレベーターのボタンの位置を低くし、鏡をつける。
点字ブロック、バリアフリートイレ、建物の入口には十分な幅のスロープなど、障害のある方が使いやすいようにハード面のバリアフリー化が広がってきました。
しかしそれだけでは社会のバリアはなくなりません。
私たちにとって重要なのは(4)の意識上のバリアをなくすことです。
障害のある人に対する無理解。
かわいそうな存在と決めつけたり、点字ブロックの上に無自覚に立ったり物を置いたりすることで、バリアをつくってしまいます。
大切なのは、一人ひとりの「心のバリアフリー」です。
困っていそうだけど、何に困っているかわからない。
そんな時は、「何かお困りですか?」「何かお手伝いしましょうか?」など、まずは勇気をもって行動することです。
お互いにうまく伝わらない場合は、周りに助けを求めることも必要です。
断られることもあるかもしれませんが、自分でできる、やりたい人もいるので、相手の気持ちを尊重します。
例えば電車で高齢の方に「どうぞ」と座席をゆずったところ、断られてしまった例がありました。
高齢の方は、「次の駅で降りるから、一度座ると立つのがたいへんだから」と言います。
私たち介護職は経験からその方の不安がよく理解できます。
それでも声を掛けてみないとわからないことです。
聴覚障害の方は、事故などでの車内アナウンスがあっても情報が伝わりません。
筆談だけでなく、スマホで文字にするなど方法はあります。
最近ではテレビの字幕放送もあり、バリアフリー上映に対応できる映画館も少しずつ増えてきました。
観光地でも、「観光施設における心のバリアフリー認定制度」が2020年に創設されています。
障害のある人、高齢で生活が困難な人だけでなく、妊娠中の女性やベビーカーで子どもを連れた人など、全ての人が快適に暮らし、平等に参加できる社会や環境、バリアを理解して自分にできる行動を続ける「心のバリアフリー」。
介護職の私たちは、知識と経験から配慮や気配りが身についています。
誰もが安心して、さまざまな活動を楽しめる社会を心がけていきたいと思います。